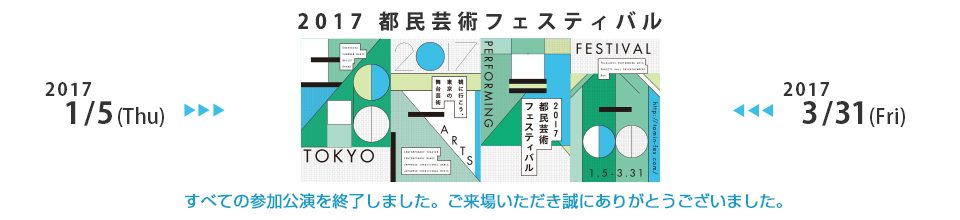2017都民芸術フェスティバル 公式サイト
人間のドラマを描く演劇の魅力

永井 愛(ながい あい)さん
永井 愛(ながい あい)
劇作家・演出家。二兎社主宰。桐朋学園芸術短期大学演劇専攻卒。
「言葉」や「習慣」「ジェンダー」「家族」「町」など、身辺や意識下に潜む問題をすくい上げ、 現実の生活に直結した、ライブ感覚あふれる劇作を続けている。
1996年『僕の東京日記』で第31回紀伊國屋演劇賞個人賞、1997年『見よ、飛行機の高く飛べるを』『ら抜きの殺意』で第48回芸術選奨文部大臣新人賞、『ら抜きの殺意』で第1回鶴屋南北戯曲賞、1999年『兄帰る』で第44回岸田國士戯曲賞、2000年『萩家の三姉妹』で第52回読売文学賞・第8回読売演劇大賞優秀演出家賞等、2001年『こんにちは、母さん』『日暮町風土記』で第1回朝日舞台芸術賞秋元松代賞、2005年『歌わせたい男たち』で第13回読売演劇大賞優秀演出家賞、2014年『鴎外の怪談』第2回ハヤカワ「悲劇喜劇」賞・バッカーズアワード演劇奨励賞・第65回芸術選奨文部科学大臣賞受賞。
日本の演劇界を代表する劇作家の一人として海外でも注目を集め、『時の物置』『萩家の三姉妹』『片づけたい女たち』『こんにちは、母さん』『歌わせたい男たち』など多くの作品が、外国語に翻訳・リーディング上演されている。
永井さんは1981年に大石静さんと「二兎社」を創設されて以来、劇作家・演出家として第一線で活躍されています。これまでのご活動についてご紹介ください。
小さな頃から表現意欲があって、幼稚園のお遊戯会で周囲の子が「人前で踊るなんて恥ずかしくてできない」と泣き出してしまうような時代に、ノリノリで「やります!」と言う子どもでした。お遊戯会の表現空間や非日常性が楽しくて、終わってからも近所の家を訪ねては、玄関先で踊ってみせたりしてましたね(笑)。私は今日の夕食に、肉と魚のどちらを食べようかってことすら、なかなか決めらないたちなのですが、演劇をやりたいということだけは、小さな頃から何も迷わず決めていました。それで俳優座に入りたいと思い、桐朋学園芸術短大には、俳優座養成所が移行した演劇科があったので入学したんです。ところがその頃アングラ演劇が盛んになり、新劇的なリアリズムとは違った、わけのわからない、でも身体的な躍動感に満ちた演劇が登場したことで、俳優座を受ける気がなくなってしまったんです。かといってアングラに飛び込む勇気もなく、前衛劇団の安部公房スタジオを受けたものの落ちてしまい、その後はアルバイトをしながら、役者への道を模索していました。ようやく小さなグループに拾われ、そこで大石静と出会ったのですが、そこも2年ほどで解散。友だちの劇団に出してもらったりするうちに、「じゃあ二人でやろう」となったわけです。「もう私たちを待っているものは何もない、だから自分で書いて出るしかない」と。その判断は、間違ってなかったですね(笑)。そして、初めて戯曲を書いてみたら、演技とはまた違った、世界の色が塗り替わるくらいの創造の喜びを味わって。次第に演じるのがつらくなってきたんです。自分が演出していると、役者としての私は誰からも何も言われませんから、だめな俳優になっていくだけだなと思って。こうして紆余曲折ありましたが、1995年からは劇作と演出だけに専念するようになりました。
今回の新作『ザ・空気』は、テレビ局の報道現場を舞台に、現代日本を覆う奇妙な空気と、それに翻弄される人々を描かれた作品です。この作品を上演されることになった経緯をお聞かせください。
もともと日本の言論の自由を巡る風景を描きたいと思っていました。そこから報道に絞った過程には、2016年2月に総務大臣が衆院予算委員会で、放送局が政治的な公平性を欠く放送を繰り返したと判断した場合、放送法4条違反を理由に電波法76条に基づいて電波停止を命じる可能性に言及した一件がありました。でも、「政府に賛成ばかりするから電波停止」というのはまずない。政府が通そうとする法案に対してノーという報道をしたり、反対の立場の人をたくさん出演させたりすることを繰り返した場合への「電波停止」を想像させますから、これは報道の独立性に対する圧力になりますよね。欧米の民主主義国だと電波の許認可を管轄するのは、政府から独立した委員会なので、海外からは「日本は電波の許認可権を政府が握っているのか」と驚かれました。また、「意見及び表現の自由」の調査を担当する国連特別報告者デビッド・ケイ氏が来日して調査した結果出した結論は「日本の報道の独立性は重大な脅威に直面している」でした。それは政府からの直接的間接的な圧力、それからメディア内部の自己規制のためです。メディア上部が閣僚と食事をする間柄では、政府に都合の悪い記事は掲載されにくくなる。そうやって情報がシャットアウトされると国民は考える契機を失い、主権者としてよい選択ができなくなります。だから報道の独立性というのは大事な問題なのだと改めて感じ、このテーマで書いてみようと思いました。
今回上演する作品にも使われている「空気」ですが、日本人って「空気を読む」とか「言える空気じゃなかった」という言い方をするでしょう。言論の自由が憲法で認められているにも関わらず、個として自由に発言することをためらう。そういう自己規制体質というのは、メディアに限らず日本人全体が持っているものだと感じます。ですから、メディアだけの問題ではないものの、メディアがそれをやってしまうと、国民の知る権利が侵されてしまう。私たちの生死に直結するようなことが知らされないまま起きてしまうのは怖いことです。こういう状況の中に登場人物を置いて、その「空気」を描いてみたくなりました。
出演者のみなさんのご紹介をお願いします。
今回はみなさんすべて、初めてのメンバーです。田中哲司さんとはずっと前から一緒にやりたいと思っていて、ようやく実現しました。民放のニュース番組のプロデューサー、編集長、ディレクター、キャスターといった役割の中で、最初はプロデューサー役でと考えていたんです。でも、田中さんは柔らかいけど強さもあり、ピュアな感じもするけど迷いも見えるという多様な人間性を滲ませる方なので、苦悩する編集長こそふさわしいと思いました。キャスター役の若村麻由美さんも、知的でコミカル、凛としていながら謎めいてもいるなど、多様な魅力を発揮する方ですよね。今回はちょっと芯があるというか主張の強い役ですが、もろさや苦悩も同時に伝わってきて、さすがだと思います。木場勝己さんは、出演されている舞台を観るたびに、その演技、存在感に感銘を受けてきました。保守系のアンカーで、表面はものやわらかなんだけど、なかなか食えない人っていう役、すごく面白いですよ。江口のりこさんはテレビでも活躍され、今注目されている方ですね。江口さんのような脱力系クールなタイプって二兎社の作品にこれまであまり出たことがないのですが、今回はディレクター役でいい味を出してくれています。大窪人衛さんは私のワークショップに参加してくれたのがご縁で知り合いました。その時とてもおかしいことをするというか、発想にユニークなところがあって、編集マン役で出てもらうことになりました。
このメンバー、われながら本当にいいキャスティングだったと思います。みんな自立していて、ちょっと言うだけで、さらなる答えを出してくれる人たちなので、とても面白いですね。私の本が遅かったせいで死ぬ思いをしたと思いますが(笑)、それにもめげず立ち向かう姿には、本当に頭が下がりました。
戯曲を書かれる時や演出される際に心がけていらっしゃるのはどんなことでしょうか。

自分が観客として、何の予備知識もない状態でこの芝居を観たとき、面白いと思うだろうかということを、必ず目を閉じて考えます。そして私が面白いと思うものであれば、ほかの人がつまらないと言っても勇気をもって書こうと思います。
また演出では、作・演出の両方をやると、どうしても思い込みが強くなるので、役者さんが出してきたプランというか、私の書いたものをどう受け止めたから、こういう表現が出てきたのかということをまずは受け入れるようにしています。それが、自分が最初にイメージしていたものと違っても、いきなり「そうじゃない」と否定しない。最終的に、自立的になった役者がいちばん素晴らしいんです。時間をかけるほど、役者はどんどんその役の専門家になっていき、作家も演出家も見つけられないものを見つけるんですよ。演出はそこに到達するまでの橋渡しですね。だから私は最初こそ細かく言いますが、それは自由になってもらうため。その後はもう安心して任せられます。劇作家・演出家として、その状態になる前に芝居の幕を開けるということは、何よりも罪深いことだと思います。今回はそういう意味でも役者さんに助けられています。
テレビや映画、舞台を使った多様なエンターテインメントがあふれる現代の東京で、演劇作品を上演するということに、どのような意味があるとお考えでしょうか。
舞台には子どもの時に、新しいものを目にしてわくわくするような、原初的な遊びの面白さがありますよね。例えば今回の芝居では舞台美術にエレベーターを使っているんですか、映像でエレベーターが出てきたって何てことないでしょう? けれど舞台では、裏側で人が動かしているわけです。自動っぽく見せるために、裏方さんがドアを開けたり閉めたり、タイミング合わせて音響さんが音を鳴らして。人間が上手に機械のふりをしているのが、私は可笑しい。スピルバーグが監督して、『戦火の馬』という邦題で公開された映画の元になった舞台、『ウォー・ホース』をロンドンで観ました。映画では生身の馬が出ているわけですが、舞台では等身大の馬のパペットを、文楽みたいに3人がかりで動かしているんですよ。それが素晴らしい動きで、大好きな少年が出てくると、全身で喜びを表す様子なんか、本当の馬以上に馬らしくて、何ともいえない感動がありました。演劇というのは、こういう子どもの遊びみたいなものが人を驚かせたり喜ばせたりするという、最も素朴な人間のハートに直接語りかけるものかなと思います。
それから映像と違って、演劇は観客と一緒に作るものです。映像は観客が寝ていようが最後まで変化はありませんが、舞台は観客の半分以上が寝たら、確実に出来が悪くなります。舞台は視線に支えられているものなんですね。客席から見られている緊張感の中で、演技への集中を高めることによって、稽古場では起きなかったことが起きたり、新たな発見があったりする。ですから、観客は芝居に良くも悪くも大変なパワーを与えているんですよ。演劇とは、観客と表現者が一緒に創造の時間を過ごすという、体験型の芸術です。一番古いメディアであるという誇りを持ちつつ、素朴な魅力を活かして、生き続けてもらいたいと思います。
観客の方へのメッセージをお願いします。
私は喜劇を書くことが多く、客席から笑いが起きることを大きな喜びとしているのですが、今回の芝居はあまり笑いが起きないです。喜劇というより、スリリングな展開になっているので、当たり前なのかもしれませんが、題材的に笑うとまずいかなと思う方がいらっしゃるのかもしれません。好き嫌いがわかれる題材だとも思います。報道の自由に関心がなければ、何をこんなに騒いでいるのかもわからないですよね。けれど、これは勉強ではなく芝居ですから、人間のドラマとして、まずは楽しんでいただきたいです。その上で、皆さんにつながる世界の問題として感じ取っていただけたらうれしいです。
ページの内容終わり